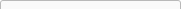「ねぇねぇ、結菜ぁ。腋の下より
もっと匂いのキツイところ舐めたくなぁい?」
杏子は彼女の頭を優しく撫でながら声を掛けた。
「はぁぁん、舐めたいですぅっ……!」
口の周りを唾液塗れにした結菜が
嬉しそうに顔を上げる。
「うふふふっ。じゃあさぁ、
私の足の指舐めてよ。
昨日からお風呂入ってないし、
靴下もずっと穿きっぱなしだったから、
きっとムレムレですっごい匂いすると思うの」
「あぁっ! それ、すっごく素敵ですっ!
杏子さんのムレムレの足、舐めさせて下さいっ!」
「うっふふふ。素直でイイコねぇ、
結菜は。待ってて。今靴下脱いじゃうからね」
杏子は右足を引き寄せ、
穿いていたカラフルなダイヤ柄のソックスを
ずり下げていった。
ソックスの爪先(つまさき)を引っ張って
足から抜く。形良く揃った足の指が露になった。
爪に塗られたペディキュアは明るめの赤。
そんなセクシーな足の指が、
汗ばんでふやけたように色を変えている。
靴下を履いたまま二度も気をやっているだけあって、
いつも以上に蒸れてしまっていたようだ。
そんなネトつきすら感じさせるような
足先を持ち上げ、
ハァハァ息を荒げている結菜の口元へと
差し出してゆく。
「あ……あ……。杏子さんの……足…
…。おいしそう……」
あまりの興奮からか、彼女はもう、
まぶたが半分閉じたようなうつろな眼になっている。
頬もすっかり上気した状態だ。
「ほぉら、好きなだけ舐めていいよぉ……」
足の親指で、後輩の濡れた唇をつぅっとなぞる。
彼女の呼吸が次第に短く、浅くなっていくのがわかる。
「はっ……はっ……はっ……!」
結菜の両手が杏子の素足を掴んでくる。その直後だった。
かぷりっ……!
彼女の愛くるしい唇が、
とうとう匂い立つ爪先を咥え込んだ。
「んっふぅぅぅぅーっ!」
結菜の鼻から熱い溜め息が漏れ、
足の甲をしっとりと潤わせた。次いで、
温かい舌がヌルヌルと足指を這い始めた。
「どう? おいしい? 私の足」
「はむぅっ! はむぅっ!」
杏子の足先をめいっぱいに頬ばったまま、
ほとんど白目を向いたような表情で結菜が頷く。
蒸れ切った足の匂いに頭がオーバーヒートして、
半ばイッてしまった状況になっているのだろう。
そんな中で、
彼女の舌だけは確かな意志を持って
足指にまとわり付いてきていた。
(あぁ……。
なんていやらしい舌遣いをしてくるのかしら、
この子……!)
指の股を這い回る生温いヌメつき。
爪先をとろけさせるような口腔内の妖しい湿度。
ただ足の指をしゃぶられているだけなのに、
信じられないほどの歓びを杏子は感じていた。
「んるるっ! チュプププッ!
じゅるるっ! ジュプププッ!
」
「んっ……! ふぅっ……!
んぁッ……! あふぅっ……!」
足指をしゃぶり立てられるたびに、
まるで性感点を刺激されているかのような
悩ましい声が漏れてしまう。
彼女の舌の動きに合わせてピクン、ピクンと
身体が震える。切なさが高まり、
股間の奥がキュンキュン熱くなってくる。
(あぁんっ、どうしようっ!
私も結菜の足舐めたくなってきちゃったっ!)
先程から結菜に舐めさせてばっかりだったせいで、
なんだか口の中が物足りなくなり始めていた。
そこへきてこの性欲を炙り立てるような口撃だ。
杏子の気持ちは
収まりが付かないくらいに膨らんでいた。
「はぁっ……! 結菜ぁ、
私にも結菜の足ちょうだい……!」
興奮で呼吸が苦しくなってくる中、
どうにか絞り出すようにして自分の思いを伝えた。
「んじゅるぅ……!
はぃぃ、杏子さんも舐めて下さいぃ!」
爪先から口を離して結菜が言う。
彼女の唇から垂れた唾液の雫が、
つつーっと卑猥に足の裏を伝っていった。
「待ってて下さいね、今あげますから……」
ベッドの上で
正座するような姿勢になっていた結菜が、
静かに足を崩してゆく。
彼女は杏子の足先を持ったまま後ろに
倒れるようにして、
紺色のソックスに包まれた右足を差し出してきた。
「あふぅ……結菜の足ぃ……!」
結菜の足をつかんだ杏子は、
すぐさま顔を押し付けていった。
ジケジケと湿気を帯びた布地に
鼻を擦り付け、深々と息を吸う。
ブーツの中でムレにムレていた足の匂いが、
鼻腔から脳天へと突き抜けていった。
「ふはぁっ……! すごい匂いっ……!
いいーっ!」
納豆を燻じたような格別の薫りが、
杏子の脳をとろめかせた。
鼻腔の粘膜がカァッと火照り、
眉間の奥がズゥンと心地よく痛んだ。
同時に、
足先がまた温かな粘膜に包み込まれるのを感じた。
右足を杏子に預けた結菜が、
再び足指への奉仕を始めたのだ。
しかも今度は、指の一本一本を
丁寧に舐めるような熱の入れようだった。
(やぁんっ! この子、
爪の脇にまでベロをねじ込んで舐めてるっ!)
そこまでされてしまっては、
杏子のほうも自制心が揺らいできてしまう。
「はっ……はっ……はっ……!」
激しく呼吸を乱しながら、
結菜のハイソックスをはぎ取ってゆく。
足先から抜いたソックスは、
二、三度匂いを嗅いでからベッド脇に放り投げた。
普段であれば、脱がせたソックスを
口に含んだりして楽しむところなのだが、
これほどまで気持ちが高まってしまっては、
匂いの元を直接味わわないことには収まらなかった。
杏子は目の前に晒された結菜の素足を
じっと眺めた。
ナチュラルなペディキュアの塗られた足指が、
自分同様に湿気った色合いを見せていた。
今日、この部屋へ向かう直前まで
ファミレスでの立ち仕事を続けていた結菜。
しかも、自分と同じく、
昨日はお風呂に入っていないのだ。
いつも以上に汗ばんだ状態のまま
フロアを歩き回っていたこの足は、
果たしてどれほど熟成が進んでいるのだろうか……。
そう考えただけで、
口の中に唾液が湧き出してきてしまう。
彼女の指の先に、そっと鼻を近づけてみる。
「あふっ……!」
想像を絶する強い匂いが鼻腔を打ち、
杏子は反射的に顔を離した。
納豆の発酵を数段激しくしたような、
恐ろしく濃厚な薫りが湯気のごとく立ち昇っていた。
(この足を、こんなに濃い匂いのする足の指を、
今から口に入れてジュポジュポ
しゃぶるんだっ……! こんなの舐めたら、
私どうなっちゃうんだろうっ……!)
狂的な歓びで胸がブルブルと震えてきた。
股間の奥にどぷっ、と熱い潤みが染み渡る。
もう、舐めないではいられなかった。
「ん……ぁ……ぁ!」
大きく口を開き、
やや巻き爪気味の足の親指を咥え込んでいく。
じめっとした指の感触が唇に触れた。
そのまま口をすぼめて吸い上げつつ、
ねっとりと舌を絡めていった。
舌腹に、ほのかな塩気を感じた。
そして一瞬の後……!
「むっ……ふぅぅぅぅぅぅぅーっ!」
凝縮された只ならぬ匂いが口に溢れ、
頭の中で爆発が起った。
(何これっ……! 最高だわっ!
頭がおかしくなりそうーっ!)
瞼は開いているはずなのに、
目の前が真っ白になって何も見えなくなった。
さらに、まるで絶頂した時のように、
ヒクン、ヒクン、と子宮が収縮し始めていた。
何が起ったのか、
杏子はまったく理解出来なかった。
視界は完全にホワイトアウトしていて、
自分が立っているのか座っているのかもわからない。
ひょっとしたら
宙に浮いているんじゃないかと思うほど、
身体の重さも感じなかった。
やがて白い光が弱まってきて、
徐々に自分のいる場所が判別できるようになった。
そこは、いつものベッドの上だった。
しかし、胸を満たす幸福感だけがいつもと違っていた。
(もしかして私、今イッちゃってたのかも……!)
まったくもって始めての経験だった。
身体がイッたのではなく、
脳中枢がイッてしまったような感覚。
そんなかつてない心地良さに、
杏子は呆然と浸り切っていた。
(あぁ……。興奮で頭がぶっ飛ぶって、
こういうことなんだ……。
本当に限界まで嬉しくなっちゃうと、
人間ってこんな風になっちゃうのね……)
とにかく、
今この瞬間が気持ち良くてしょうがなかった。
まさに、生きていることの歓びそのものを
味わったような気分だった。
おしっこを漏らしていないのが不思議なくらいだ。
(はぁぁっ、あなたの足、最高よ……!)
杏子は、
こんな素敵な感覚をもたらしてくれた後輩の足に、
感謝の思いを込めて唇を寄せていった。