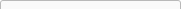女子大生・杏子(きょうこ)と女子高生・結菜(ゆいな)
土曜日の夜。
自室のベッドに腰掛けた杏子(きょうこ)は、
モジモジと切なげに太腿の間を擦り合わせながら、
後輩の結菜(ゆいな)が来るのを待っていた。
時計の針は二十二時を少し回ったところ。
約束の時間から、もう三十分も過ぎていた。
杏子はふぅっ、と溜め息をついて下を向いた。
ストレートの黒髪が肩から流れ落ち、
その凛とした顔立ちを陰らせる。
到着が遅くなりそう、というメールは、
もちろん結菜から送られてきていた。
人身事故で電車が止まってしまった。
その止むを得ない状況も、十分理解していた。
それでも杏子は、モゾモゾと太腿を動かすのを
やめられなかった。
アノ部分が、どうにもムズついて仕方ないのだ。
今日という日のために、
昨日からお風呂に入っていなかったせいで……。
ワンピースの下のパンティは、
おとといから穿き替えていない。
それどころか、トイレでは
ウォシュレットすら使わないようにしていたのだ。
おまけに週末結菜と会うことを思って
アソコが潤み、そして渇き……
というサイクルを何度も繰り返してきたおかげで、
その部分は自分でも驚くくらいの量の
恥垢に覆われていた。
(結菜……。早く来てよぉ……。
私のあの場所、早くキレイにして……)
杏子は、一つ年下の可愛らしい後輩が、
うっとりした表情で自分の股間を
舐め回しているところを想像していた。
太腿の間で、ショートカットの髪を揺らしつつ
ハァハァと息を乱す結菜。
温かくて柔らかい舌が、ネットリした白い汚れを
ペロペロと舐め取っていくその感触、
その満足感……。
「は……ぁ……」
そんな情景を頭に思い描いているうちに、
知らず知らず股間に指を這わせてしまいそうになる。
「……はっ!」
ワンピースの裾に指がかかったところで
我に返り、慌てて手を引っ込める。
こんな発情した状態が、
先程からずっと続いていた。
(どうしてくれるのぉ……。
このままじゃ私、おかしくなっちゃうよ……)
我慢が限界に達しようとしていたまさにその時だ。
ピンポーン
という明るい音を立てて、
部屋の呼び鈴が鳴らされた。
「来たっ!」
慌てて玄関へ飛び出してゆく杏子。
ワンルームの短い廊下を走り抜け、
ドアの覗き穴すら確認せずに
ガチャンと鍵を外した。
ドアノブを回し、扉を開く。
待ちに待ったその相手が、
薄暗い外廊下に立っていた。
タートルネックのセーターに
紺のスカートを穿いた、ショートカットの女の子だ。
もともと大人しそうなその顔が、
遅刻した申し訳なさからかいつも以上に
気弱な表情となっていた。
「ごめんなさい、遅くなっちゃって……。
あっ……」
開口一番謝ってきた結菜の腕を掴み、
グイッと玄関の中に引き入れる。
バタンとドアが閉まり、
近くの国道を走る車の音がグンと遠くなった。
杏子は、そのまま無言で結菜を引き寄せ、
抱きしめた。
彼女のミディアムショートの髪に顔を埋める。
わずかに湿ったような感触と、
少しきつい汗の匂いがした。
「んはぁっ……。結菜の匂いだ……」
愛しい後輩の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。
汗っぽい体臭の中で、
シャンプーの残り香はほんのかすか。
結菜もお風呂に入っていないことが、
その匂いだけでわかった。
「うふふっ。約束通り、
昨日はお風呂入ってないみたいね。
私も入ってないよ。だからほら、
結菜も私の匂い嗅いで?」
「はぁっ……。
お風呂に入ってない杏子さんの匂い、
嗅ぎたい……」
背の低い結菜は、
わずかに踵を浮かせて背伸びして、
杏子の首筋に顔を寄せてきた。そうして、
肩の前に垂らされた長い髪の匂いを
クンクン嗅いでいく。
「んー……はぁぁぁ……んんー……
はぁぁぁぁ……」
視界には入らなくても、
結菜がどれほど恍惚とした表情で
髪の匂いを吸っているのかが、
彼女の深い呼吸音から感じ取れた。
「はぁぁ……。杏子さんの匂いぃ……。
んんーっ……。はぁぁぁ……」
杏子の髪の匂いに嗅ぎ惚れている結菜は、
もはや約束の時間に遅れたことなど
すっかり忘れてしまっているようだった。
そのくらい自分の世界に入り込み、
濃密な香りを嗅ぎ続けている。
(お風呂に入ってない私の匂いを、
こんなに真剣に嗅ぎ続けてくれるなんて……。
やっぱり結菜は可愛い……。こんなに素敵な子、
結菜の他には絶対いないわ……)
自分と同じ、重度の匂いフェチ。
いや、もしかしたら、
この子の方がずっと深刻かもしれない。
そんなことを思ってしまうほど、
結菜は杏子の髪の中で激しく顔をうねらせていた。
「ふふっ。ねぇ、結菜。
せっかくだからここじゃなくて部屋に行こうよ。
こんな狭いところじゃ、
できることも限られちゃうでしょう?」
結菜の華奢な肩を撫でながら、
耳元でそっと囁いた。
それでやっと彼女の息づかいが和らいできた。
「はぁぁ……。先輩の匂い、
相変わらず素敵ですぅ……」
ようやく顔をあげた結菜がうっとりと言った。
その表情は、すでに夢の中を
たゆたっているようにも見えた。
「あははっ。
何、そのいけないクスリをやってます、
みたいなぼーっとした顏」
クスリは冗談にしても、実際、
彼女の意識は朦朧となっているのかもしれない。
あれだけ激しく匂いを嗅ぎ続けていれば、
軽い酸欠になってもおかしくないからだ。
それに、今しがた結菜の呟いた
『先輩』という言葉。
これは、二人が高校のテニス部で
先輩・後輩の関係だった頃に使っていた呼び方だ。
杏子が高校を卒業し、大学生になってからは、
結菜は『杏子さん』という
言い方をするようになっていた。
にも関わらず『先輩』と呟いてしまったのは、
結菜の心だけ、二年前にタイムスリップ
してしまったからだろう。
杏子は、お互いの汗ばんだ身体の匂いを
毎日のように嗅ぎ合っていた
あの頃のことを思い出し、
ふふっ、と微笑んだ。
「ほら、早く上がってきて。あ、靴は脱いでね」
杏子に指さされ、
「あっ……!」
と足元を見る結菜。
「ごめんなさい、
私、まだ靴履いたままでしたね……」
そう言って、慌ててブーツを脱ぎ始めた。
(相変わらずこの子は、匂いに夢中になると
他のことに気が回らなくなっちゃうのね)
玄関に屈みこんでもどかしげに
ブーツの紐を解く後輩の姿を眺めながら、
杏子はきゅんと愛しさを募らせるのだった。