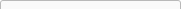アンジェリークPRESENTS
匂いフェチ官能小説
第2弾
【 工場娘の匂い 】
1/9
貪よりとした暗い町だった。
昭和時代の
古い看板を掲げる商店街は
全体的に埃っぽく、
半分以上の店は
シャッターが下り、
そこには『貸店舗』という
不動産屋の看板が
ズラリと並んでいた。
そんなゴーストタウンのような
商店街を抜け、
映画のセットのような
古い小さな駅の裏手に行くと、
そこにはただひたすらに巨大な
工場群が威圧的に並んでいる。

金石はそんな工場群の中に
ポツンとあるコンビニの、
斜め前にある
埃だらけのバス停に車を止めた。
時計を見ると四時四十五分。
そろそろ獣たちが
工場から出て来る頃だった。
金石真二は
都内の広告代理店に勤める
四十八才。
給料もそこそこ良く、
去年は念願の
企画部長にまで昇進した。
二つ歳下の妻は
近所でも評判の器量良しで、
三人の子供は元気で素直で
金石の事を心から尊敬している。
毛並みの良い
ゴールデンレトリバーが走り回る
庭付き一戸建てのマイホームも
そろそろローンが終わる頃で、
それが終わったら、
老後の事を考えて
鎌倉に小さな別荘でも
ひとつ欲しいね、
などと妻と話し合う金石は、
仕事と家庭においては
幸せを絵に書いたような男だった。
しかし、そんな金石にも
問題があった。
それは金石の
異常なる性癖である。
金石は子供の頃から
匂いフェチだった。
もちろん、
自分が匂いフェチだ
という事を知ったのは
大人になってからだが、
しかし、その異常性癖の兆候は
彼が子供の頃から
既に芽生えていた。
彼が女の匂い
というものに
性的な興奮を覚えたのは、
まだ金石が
中学二年の頃だった。
ある日、
風邪気味だった金石は
体育授業のプールを休み、
校舎の窓から聞こえて来る
生徒達の
楽しそうな笑い声を聞きながら、
一人教室で黙々と
漢字の書き取りをしていた。
そんな金石は、ふいに、
教室の机の上に畳んである
女子達の衣類が
気になって仕方なくなる。
そして遂に
こっそり女子の衣類を
物色してしまったのだ。
机の上の制服の中に
手を突っ込み、
畳んである制服が崩れないよう
慎重に弄りながら
下着だけを上手に取り出した。
ほとんどの女生徒の下着は
白だった。
それを広げて裏返し、
その白い布地に付着している
黄色いシミを見ては、
金石は
自分だけがその女生徒の
秘密を知っているんだ
という優越感に
浸っていたのだった。
それが癖になった金石は、
その後のプールは
毎回欠席し
女生徒の下着を物色した。
夏休みに入ると
益々エスカレートした金石は、
学校のプールにやって来た
女生徒達が
衣類を脱いでいる
体育館へと忍び込み、
女生徒達の
ビーチバッグの中を漁った。
ある時、そんな金石は、
三年生のビーチバッグの中から
白と青のボーダー柄の
パンティーを発見した。
それは、
手の平の中にすっぽりと収まるほどの
小さなパンティーで、
今までに白い大きなパンツしか
見た事の無かった金石は
強烈な衝撃を受けた。
金石は迷う事無く
それをポケットの中に
押し込んだ。
そしてバッグに書いてある
三年A組笠井恵子
という名前を
頭に叩き込んだのだった。
家に持ち帰り、
さっそくパンティーを広げて見た。
パンティーの裏側には、
まるで筆でシュッと
殴り書きされたような
一本線のシミが付着し、
それは卵焼きのような
色をしていた。
金石はその黄色いシミに
恐る恐る鼻を近づけてみる。
今までの金石は
見る事だけを楽しみとしており、
それを嗅いだり舐めたり、
ましてそれを見て
自慰に耽ることなど
一度もなかった。
それまでの彼は、
ただ女生徒の秘密を知ったと言う
優越感だけで
満足していたのだ。
二センチほどの黄色いシミに
鼻先をあてては
クンクンと嗅いだ金石は、
そのあまりの臭さに
「うわっ!」
と仰け反り、
おもわずそのパンティーを
壁に投げつけてしまった。
(まるで・・
父さんがいつも晩酌で食べている
スルメイカのようなニオイだ・・・)
それで興醒めしてしまうのが
正常な男子だが、
しかし金石は違った。
あまりの臭さにびっくりして
投げ捨ててしまったものの、
しかしその
鼻がひん曲がるような
強烈な臭いを
もう一度嗅ぎたい
と思い始めた金石は、
本棚の下で丸まっている
そのパンティーを再び手にすると、
そのなんともいえない
不潔なニオイを
クンクンと嗅ぎながら
オナニーしたのだった。
それからの金石は、
女生徒の下着だけでなく、
体操服や上履きやリコーダー
といった物にまで
見境無く
手を出すようになった。
その癖は
高校や大学でも治らず、
今の会社に入社してからも
まだ続いていた。
会社の女子トイレに潜入しては
汚物入れを漁り、
誰の物かもわからない
オリモノシートを
平気で舐めたりする。
ある時など、
残業でひとり会社に残った金石は、
同じ部の事務員をしている
中川貴子の机を物色し、
その机の引き出しの奥に
隠すように保管してあった
新品のオリモノシートを見つけ出すと、
それをひとつひとつ
袋の上から
シャープペンの芯を
プツっと突き刺した。
薄いビニールの袋に
ほんの少しだけ穴が空き、
その中の白いオリモノシートには
シャープペンで
微かな印が付いていた。
これで、そのオリモノシートが
中川貴子の物だとわかる
と微笑んだ金石は、
次の日から、
中川貴子がトイレに行く度に
ソワソワとしながら後を付け、
中川貴子がどの個室に入ったか
を確認すると、
その日の夜には
その個室から
汚物入れごと盗み出し、
その中でジメッと萎れている
印付きのオリモノシートを
発見したのだった。
翌日金石は、
手の平の中に隠し持っている
オリモノシートのニオイを
こっそりと嗅ぎながら
中川貴子を見つめた。
(あんなに
綺麗な顔をしているのに
アソコは腐った魚のような
ニオイだ・・・・)
そんな事を思いながら
中川貴子を見つめ、
時にはわざとらしく
中川貴子に
話し掛けたりしながら、
金石は
その中川貴子の秘密を
自分だけが知っているんだ
と言う優越感に浸っては
ムンムンと欲情して
いたのだった。
次へ